このブログはインパクトと信頼性UPのため、ちょっと盛った「東大卒の英才教育」というタイトルにしていますが、東大卒なのは夫だけです。
そして、夫は子どもの取り組む教材を選んだり、記事をチェックしているだけで、実際に記事を書いているのは別の大学を出ている妻の私です。(誤解された方がいたらすみません)
突然ですが、私の学歴は、地方の公立小中高→出身地の国立大です。
小さい頃から勉強はまあまあ得意だったのですが、学校にあまり良い印象はありません。
今までそれがなぜかよく分からなかったんですが、先日『勉強できる子 卑屈化社会』という本を読んで腑に落ちた部分がありました。
※2016年12月に発売の本なのですが、当時は赤ちゃんのお世話に忙しくて知りませんでした。
この本は「日本には勉強ができる子を色眼鏡で見る風潮があり、スポーツなどと違って大っぴらに自慢できない後ろめたいものになっている。そのせいで卑屈になったり勉強の才能が伸び悩んだりする子達がいて国力を下げている」という内容です。
特に田舎においてこの傾向が強いようです。
この本の中で具体的にどんな「勉強ができる子の不遇」が紹介されているかというと、
学業成績がよいことを口に出せば必要以上に自慢ととられ、謙遜すればしたでそれも嫌味ととられる
スポーツのできる子と比べて、勉強できる子への謙遜圧力は明らかに強い気がする
周囲の大人に「勉強なんてできても社会では役に立たないぞ」「勉強ができるのと、頭がいいのは違うぞ」「もっと子供らしくしていいんだよ」「子供なのになんか理屈っぽいな。今からそんなんでどうする」などと言われる
上記のような例がこれでもか!と出て来ます。本文中には大げさだなと思う部分もたくさんあります。本のタイトル「卑屈化」も言い過ぎかなと思います。
報告例の少ない体験を、よくあることのように断定しちゃっていて気になるところもあります。
しかし、すごく共感できる部分もありました。心に突き刺さるエピソードがいくつかありました。
本を読んでいると、自分がそこそこ勉強ができたことによって経験した嫌な思い出がよみがって来ました。
私と夫の勉強に関する嫌な思い出の例
・小学生の頃「〇〇ちゃんは勉強ができるからいやだ」とお友達に面と向かって言われたことがあります。
冗談ぽく言われたのですが、びっくりしました。
・中学生の頃「〇〇さんは社会でいつも満点を取るから、社会の先生(独身男性)とできてる」と男子にからかわれたことがあります。社会のテストは全部板書から出題されていたので、情報をリークされなくても満点は取れたのですが。
教育熱心な東京で生まれ育って中高一貫校に進んだ主人はお友達との間でそれほど嫌な思いはしたことがないようですが、一部の教師には嫌われていたと言っています。
例えば小学生の頃、担任の代理で来た教頭に「おまえがしゃべると授業にならないから、授業中は黙っていなさい」と言われたことがあるそうです。
勉強ができることは得の方が多いのでは?
この本にも書いてあるのですが、「勉強ができることにはメリットの方が多いのではないか」と思われる方も多いと思います。
私も、勉強ができることは成人してからはかなり得だと思います。(就職や結婚など)
ただ、特に小中高において勉強界がスポーツ界や音楽界のようにキラキラした「日の当たる場所」ではないことは事実だなと思います。偏見かもしれませんが、勉強ができる子の中には陽キャラより「陰キャラ」の方が多いのではないかと思います。
学校は主に勉強に行く場所であるはずなのに、勉強を頑張っている子がそこで輝けないのは変ですよね。
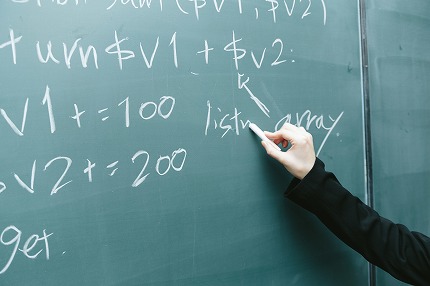
どうしてこうなった?
勉強ができる子がどうして日本で冷遇されているのでしょうか。
著者はいろいろな原因を指摘しています。その一部をご紹介します。
・日本に昔からある「出る杭は打たれる」風潮
・「勉強は強制されるのもので、スポーツは自発的にやるもの」という先入観
・「学校の勉強内容に価値があるのか」という疑問を持つ人の増加
・TVなどで不良が美化され、勉強ができる子はあまりよく描かれて来なかった背景
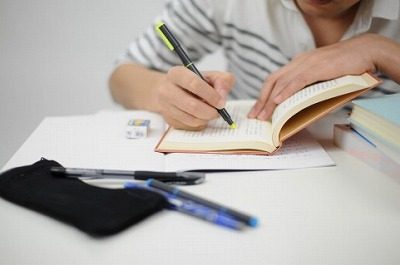
この問題に対する解決策はある?
この問題について本文で示されている解決策の一部をご紹介します。
・大人たちが勉強ができる子を、他の才能を持つ子と同様に、素直に褒める。
・世間が学校の勉強に持つイメージを更新する。
(今でも「詰め込み教育」をしているイメージがあるが、実際は灘などの進学校では「思考力」を育てる教育をしている)
・「早くに勉強の才能を示す子」以外にも平等な機会を与える。
(勉強以外の能力の評価、後から追いつくための手段の確保、人生のどの時点からでも学び直しを可能にするなど)
本文では単に比較例として紹介されているだけですが、上海のように「勉強を頑張る子と、スポーツを頑張る子を分ける」というものありだと思います。
私の考えた解決策
この問題についてド素人ながら、私も解決策を考えてみました。
・小学校から飛び級できるようにするか、習熟度別授業を大幅に取り入れるか、飛び抜けてできる子とできない子は特別授業(取り出し授業)を受けられるようにする。
・勉強ができる小学生が活躍できるクイズ番組『全国小学生No.1超頭脳決定戦!日本一頭が良い小学生は誰だ!』などのレギュラー化。
視聴者は高学歴の芸能人が出てくるクイズ番組には飽きたかもしれないが、リアルな小学生が知力を競うことには需要があると思う。
・主人公が青春を勉強かそれに類するもの(例:『ちはやふる』の百人一首)に捧げる漫画を、『少年ジャンプ』や『コロコロコミック』や『ちゃお』や『りぼん』などに載せる。できれば大物漫画家に描いてもらう。
・「がり勉」という言葉のイメージを向上させる。公共の場ではできるだけ蔑む意味で使わないようにし、良いイメージの用例を広める。なんなら英語に「Gariben」という外来語として良いイメージで取り入れてもらってもいい。
・勉強ができる子はできれば見た目にも気を遣う。最近話題の科学者、落合陽一さんは、服にもこだわっている(ヨウジヤマモトの服を愛用)ことでさらにマスコミ受けしていると思う。
・できる子の親は、自分の子を守る。他の大人や子どもに心ないことを言われたら親が反論したり、受験や留学という道を模索するなど。この本に書かれている「勉強ができる子の処世術」(=相手の話をよく聞く、相手を褒める、海外に目を向けるなど)を子どもに教えるのも大事と思う。




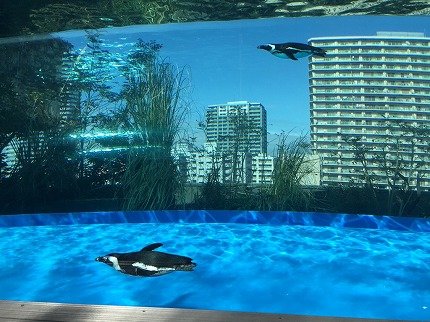
コメント
自分も学校内で勉強ができるほうだったのですが、頭の良い子が卑屈になる、というのはちょっと意味合いが違うかも。授業中自分の発言が多めだなと思ったら黙っとこうなど場の雰囲気をよんでいました。旦那さんは場の雰囲気を読まず言いたいことをずばずば言ってしまうから一部の教師に嫌われたのかもしれません。教室という常に同じメンバーの中で勉強するとしたら、できる人間ができない人間にも輝く場所を与える配慮が必要な気がします。でもできる子が周りに合わせなければいけないというのが卑屈だというならそうかもしれません。できる子はできる子のみがいる学校に行ったほうがのびのびできるのかも。
勉強ができる子よりもできない子のほうが卑屈になる確率は絶対高いです。できるご夫婦にはわからないかもしれませんが、自分だけできなくてついていけない劣等感を常に感じ続けると、何もかもやる気を失って人のせいにしがちになります。まだスポーツができるならまだしも、スポーツも勉強もできない子は、ほぼ卑屈になります。そういう子が集まる学校を知っているので。なので勉強ができる子が卑屈になるというのは一般的にみたら違うんじゃないかなあ。
>ほほほ様
コメントありがとうございます。
ほほほさんはコミュ二ケーション能力が高いので、自ら発言量を調整するなどして上手く適応されていたのですね。
うちの主人は確かにそういう配慮はしないし、自分の方が正しいと思ったら教師でも言い負かそうとするタイプなので、一部の教師に嫌われたのでしょうね。
「できる人間ができない人間にも輝く場所を与える配慮」はある程度必要だと思うのですが、同時に「できる人間が思う存分実力を発揮し、輝ける場」もあるといいなと思います。
「勉強ができる子よりもできない子のほうが卑屈になる確率は絶対高い」というご意見には全面的に同意です。勉強ができる子は(勉強という世間で評価される能力がある割には)卑屈になることがあるっていう程度の話だと思います。
私もブログ記事に「本のタイトル「卑屈化」も言い過ぎかな」と書いており、卑屈っていう言葉はあまり的確でないかなと思っています。
誤解を避けるなら「勉強ができる子が輝けない日本の学校」というタイトルの方がよいですかね。まあ、それだと本屋で人目を引かないので、盛ったタイトルになったのかもしれませんね。
記事おもしろく読ませていただきました。
私の場合は、中学で成績が学年トップだったのですが、「アイウエオ」から選択で答える問題で「オ」を書いたつもりが「それは『才』だ」と言われてバツにされたことがあります。
それ以来「オ」を書くときはとても慎重になります。
また先生の採点ミスを見つけて、98点のテストを99点に修正してもらったら、「まだ点が欲しいのか」と言われたこともあります。
それぞれ別の先生です。
クラスメイトからの成績に対する嫌味は「僻みでしょ」と思えても、先生からのほうが傷つき、憤慨した記憶があります。
記事を拝見して苦々しく思い出し、先生の意識改革も必要だなと思いました。
>ゆきママ様
コメントありがとうございます。
「オ」を「才」というのは完全にいちゃもんですね。
採点ミスを修正してもらったら「まだ点が欲しいのか」って言われたんですか!?
自分がミスしといてその言い草はないですよね!
取り上げた本に「勉強ができる子は先生に贔屓されているという誤解があるが、先生から嫌われているケースの方が多い」
という話があるのですが、本当ですね。
先生の意識改革は絶対に必要だと私も思います。
授業が中間層に合わせて行われるなら、下位層のケアと同時に上位層のケアもして欲しいですね。
いつも、参考にしております
プリキュアの映画をみて様子が、
心配だそうですが、うちの長女も音に敏感で今だにドライヤー無理です
嫌がることが多かったので
『ひといちばい敏感な子』
エレインNアーロン著を読みました
小学生までの具体的な対処があり
とてもよかった本です。
ツィッターをしていないので
こちらにコメントさせてもらいました。
>スポンジボブ様
コメントありがとうございます。娘さんも音に敏感なのですね。
ドライヤー、確かに耳元で大きい音がするので嫌ですね。
うちの子はストレスや不安を感じる場面で特に音が気になるようです。
以前、外の音が気になると、耳栓代わりに小さめの消しゴムを耳に詰めていてびっくりしたことがありました。
(詰まったら危ないですよね…)
『ひといちばい敏感な子』、私も読んでみます。
良い情報ありがとうございました!
はじめまして!
激しく同感しました。
私も田舎の公立出ですが、成績はクラスで一番まではいかないけど科目によっては一番、くらいでした。
それでも、中学時代は仲良しのお友達に妬まれたり、バカそうなくせに!とか言われたりしました。すごくショックで。。クラストップの男の子なんて、完全に変わり者扱いでした。
今後も更新を楽しみにしていますね。
>ももこ様
はじめまして!コメントありがとうございます。
勉強ができることで嫌な思いをした方、やっぱりけっこういらっしゃるんですね。
うちの中学でも勉強ができる子は変わり者扱いでした。
私は自分の子に小学校受験させようとは思っていなかったのですが、こういう話を聞くと、早く勉強が当たり前の環境に入れた方がいいのかなと思ってしまいます。
今後ともよろしくお願いいたします。
はじめまして。
面白い着眼点の本ですね。
完全に嫉妬社会の日本だと思いました。
勉強ができる子は、高確率で良い職業や収入に恵まれると予想されるから、足を引っ張るのでしょう。
学校の先生も高収入の部類とは言えません。この生徒が、将来自分の倍の年収を稼ぐようになるのかなと思うと、心がザワつくんじゃないでしょうか。ここまではっきりとイメージはしていないと思いますが、潜在的に年齢関係なく社会ランクを感じ取り、攻撃をしてくるのだと思います。
公立学校の先生に、どれほど東大卒がいるでしょう?大変珍しいのではないでしょうか。教育学部の偏差値はそれほど高くありません。そういった方たちに、子供は教育を受けるのです。少々差別的な言い方かもしれませんが、その現実はあると思います。
>keiko様
はじめまして。コメントありがとうございます。
確かに、勉強ができる子=将来良い暮らしをしそうなので、嫉妬からいじわるしたくなる
のかもしれませんね。
教師が自分より社会ランクが高くなりそうな子どもを無意識に攻撃したくなるというのはありそうですね。
今は教員は公務員として人気がありますが、以前は倍率が低かったですし。
的を射た質問を子どもがしたとしても、「凄い!」ではなく「生意気!」となるのかもしれませんね。
まあ落合陽一さんは学者というよりはタレントさんや広告塔だから参考にならないですけどね